![]() ボランティア関連ニュース(外部記事)
ボランティア関連ニュース(外部記事)
- 地域活性・まちづくり・観光
- 災害救援・地域安全活動
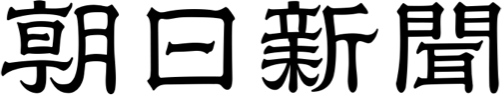
防災井戸、カフェ併設 集う場に 名張の市民センター 各地から注目
2025.04.27

大規模災害で断水などが起きた時、生活用水として使える「防災井戸」。この井戸を活用する三重県名張市内での取り組みに今、県内外から注目が集まっている。いざという時の備えだけでなく、日頃から井戸水を使ってもらおうと、カフェを運営し、多くの人が集まる場となっている。
防災井戸は「災害時協力井戸」とも呼ばれ、三重県内でも、井戸を所有する住民らが自治体に登録し、各地で非常時の備えが進んでいる。
2014年、名張市蔵持町原出の蔵持市民センターでは伊勢湾台風(1959年)の経験がある当時の自治会長の発案で、防災井戸を市の補助金で掘った。
「蔵清水の井戸」と名付けられ、毎分200リットルの水量が湧く。
災害時には無料で開放する予定で、普段は年間2千円でくみ放題。個人だけでなく、企業やパン店も契約する。1回あたりでは50円でポリタンクひとつまで利用できる。
21年からはセルフ式のカフェ「蔵清水カフェ」をセンター内に設け、井戸水を利用。インスタントコーヒーやお茶などを置き、大人100円、子ども50円のチケットを購入すれば飲み放題とし、年間1千人程度が利用する。地域のボランティアの参加者に利用券を配ったり、小中学校の長期の休みには子どもたちの自習室として開放したりもしている。
市によると、災害時協力井戸は、個人や企業、NPOなどが所有する38カ所が登録されているが、市民センター所有の井戸は蔵持だけという。
三瀬幸綱センター長(76)は「せっかく掘ってきれいな水が出たので、地域を超えて利用してもらおうじゃないかと。小中学生の居場所にもなり、幅広い世代のくつろぐ場になっている」と話す。
県外のまちづくり関係者やメディア、大学ゼミの視察もある中、食品メーカー「ミツカン」(本社・愛知県半田市)の「水の文化センター」も注目。今月23日には、年2回発行する機関誌「水の文化」の編集部員ら4人が、蔵持市民センターを訪問。経緯や活用状況を住民らから聞き取った。
水の文化センターは、「日ごろの備えと水(仮題)」の特集で蔵持の取り組みを紹介する予定。水の文化センター長の浅野修弘さん(54)は「井戸を活用してコミュニティーが生まれ、人と人とのつながりが生まれている。防災井戸はたくさんあるが、こういう所はあまりないのでは」と語る。
7月に発刊予定の機関誌はホームページから見ることができる。(小西孝司)
防災井戸は「災害時協力井戸」とも呼ばれ、三重県内でも、井戸を所有する住民らが自治体に登録し、各地で非常時の備えが進んでいる。
2014年、名張市蔵持町原出の蔵持市民センターでは伊勢湾台風(1959年)の経験がある当時の自治会長の発案で、防災井戸を市の補助金で掘った。
「蔵清水の井戸」と名付けられ、毎分200リットルの水量が湧く。
災害時には無料で開放する予定で、普段は年間2千円でくみ放題。個人だけでなく、企業やパン店も契約する。1回あたりでは50円でポリタンクひとつまで利用できる。
21年からはセルフ式のカフェ「蔵清水カフェ」をセンター内に設け、井戸水を利用。インスタントコーヒーやお茶などを置き、大人100円、子ども50円のチケットを購入すれば飲み放題とし、年間1千人程度が利用する。地域のボランティアの参加者に利用券を配ったり、小中学校の長期の休みには子どもたちの自習室として開放したりもしている。
市によると、災害時協力井戸は、個人や企業、NPOなどが所有する38カ所が登録されているが、市民センター所有の井戸は蔵持だけという。
三瀬幸綱センター長(76)は「せっかく掘ってきれいな水が出たので、地域を超えて利用してもらおうじゃないかと。小中学生の居場所にもなり、幅広い世代のくつろぐ場になっている」と話す。
県外のまちづくり関係者やメディア、大学ゼミの視察もある中、食品メーカー「ミツカン」(本社・愛知県半田市)の「水の文化センター」も注目。今月23日には、年2回発行する機関誌「水の文化」の編集部員ら4人が、蔵持市民センターを訪問。経緯や活用状況を住民らから聞き取った。
水の文化センターは、「日ごろの備えと水(仮題)」の特集で蔵持の取り組みを紹介する予定。水の文化センター長の浅野修弘さん(54)は「井戸を活用してコミュニティーが生まれ、人と人とのつながりが生まれている。防災井戸はたくさんあるが、こういう所はあまりないのでは」と語る。
7月に発刊予定の機関誌はホームページから見ることができる。(小西孝司)
