![]() ボランティア関連ニュース(外部記事)
ボランティア関連ニュース(外部記事)
- 地域活性・まちづくり・観光
- 災害救援・地域安全活動
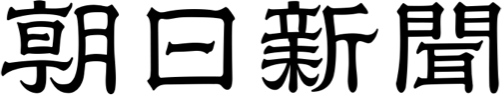
大船渡火災の対応、市民らで振り返る ワークショップ開催
2025.07.28

岩手県大船渡市で2月に発生した大規模な山林火災の初動を振り返り、今後にいかすためのワークショップが26日、同市で開かれた。大船渡青年会議所が主催し、市民ら30人あまりが集まった。
最初に、地域防災が専門の岩手大学の福留邦洋教授が講演した。「過去の災害から得た知識や教訓だけでは不十分。経験が誤った対応に結びつくことがある」として、昨年1月の能登半島地震などを例に、災害が起きた季節や地域によって対応を変える必要や、日頃から地域の住民同士がつながりを持つ重要性を指摘した。
その後、参加者たちはグループに分かれて、「避難生活」「ボランティア活動」「避難行動」をテーマに課題や良かった点を話し合った。
避難生活について話し合ったグループでは、良かった点として「東日本大震災の経験をいかして支援物資は十分あった」「避難者が自主的に避難所運営に関わった。中高生も活躍した」などがあげられた。避難所では段ボールベッドが、車中泊の避難者にはキャンプ用マットが役立ったという意見が出た。
課題としては、避難所外に避難した人たちへの支援物資の配布が不十分だったことや、避難所内でも支援物資の配布が「早い者勝ち」になった点、ペットを連れた人たちが車中泊せざるをえなかった点、感染症対策の難しさなどがあげられた。
火災で大きな被害を受けた綾里地区の30代の男性は、当時生後半年の乳児を抱えていた。「避難所での集団生活は無理だった。幼い子供がいたり、介護が必要な人がいたりした家族がどう避難生活を送ったかを検証して、今後に役立ててほしい」
東日本大震災では、生理用品など特定の人が必要な物資の不足が指摘された。今回生理用品は十分にあったが、70代の女性は「風呂に入れなかった時期におりものシートがあると役に立った」と振り返り、個々の事情に応じた支援物資の必要性を語った。
また、当時受験を間近に控えていた高校1年生の女性は「メディアが避難所に自由に出入りし、勉強中に取材を申し込まれて迷惑だった」と話した。参加者からは「取材は避難所の外でするといったルールを、あらかじめ決める必要がある」などの意見が出た。
主催した大船渡青年会議所理事長の鎌田智さんは「当時、悩みながら様々な支援を行った。同じような体験をした方々と話し合い、記録に残して、防災意識を持ち続けたい」と話した。(伊藤恵里奈)
最初に、地域防災が専門の岩手大学の福留邦洋教授が講演した。「過去の災害から得た知識や教訓だけでは不十分。経験が誤った対応に結びつくことがある」として、昨年1月の能登半島地震などを例に、災害が起きた季節や地域によって対応を変える必要や、日頃から地域の住民同士がつながりを持つ重要性を指摘した。
その後、参加者たちはグループに分かれて、「避難生活」「ボランティア活動」「避難行動」をテーマに課題や良かった点を話し合った。
避難生活について話し合ったグループでは、良かった点として「東日本大震災の経験をいかして支援物資は十分あった」「避難者が自主的に避難所運営に関わった。中高生も活躍した」などがあげられた。避難所では段ボールベッドが、車中泊の避難者にはキャンプ用マットが役立ったという意見が出た。
課題としては、避難所外に避難した人たちへの支援物資の配布が不十分だったことや、避難所内でも支援物資の配布が「早い者勝ち」になった点、ペットを連れた人たちが車中泊せざるをえなかった点、感染症対策の難しさなどがあげられた。
火災で大きな被害を受けた綾里地区の30代の男性は、当時生後半年の乳児を抱えていた。「避難所での集団生活は無理だった。幼い子供がいたり、介護が必要な人がいたりした家族がどう避難生活を送ったかを検証して、今後に役立ててほしい」
東日本大震災では、生理用品など特定の人が必要な物資の不足が指摘された。今回生理用品は十分にあったが、70代の女性は「風呂に入れなかった時期におりものシートがあると役に立った」と振り返り、個々の事情に応じた支援物資の必要性を語った。
また、当時受験を間近に控えていた高校1年生の女性は「メディアが避難所に自由に出入りし、勉強中に取材を申し込まれて迷惑だった」と話した。参加者からは「取材は避難所の外でするといったルールを、あらかじめ決める必要がある」などの意見が出た。
主催した大船渡青年会議所理事長の鎌田智さんは「当時、悩みながら様々な支援を行った。同じような体験をした方々と話し合い、記録に残して、防災意識を持ち続けたい」と話した。(伊藤恵里奈)
