![]() ボランティア関連ニュース(外部記事)
ボランティア関連ニュース(外部記事)
- 文化・芸術
- 地域活性・まちづくり・観光
- 災害救援・地域安全活動
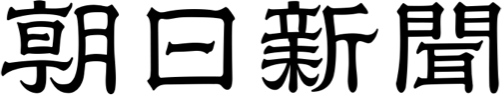
祭りまでに鳥居を 能登住民の頼みに被災経験者が860キロ通い修復
2025.08.05

能登半島地震で鳥居やこま犬などが倒壊した石川県輪島市の神社を、東日本大震災で被災した岩手県大槌町の石材業者が、860キロの道のりを往復して修復し、8月の夏祭りに間に合わせた。
大槌町の石材業・芳賀光さん(50)は、昨年元日に起きた能登半島地震の1カ月後には車で12時間かけて輪島市に行き、炊き出しなどをしていた。津波で事務所や作業所が流された経験を持つ芳賀さんは「人ごとではない」と、昨年9月の豪雨災害後も土砂の撤去など10回ほどボランティアに通った。
住民が心のよりどころにしている春日神社の鳥居やこま犬、灯籠(とうろう)、標柱などが倒壊して修復できないでいると知った。各地で文化財が倒壊し、地元業者に修復を頼むと何年も待たねばならないという。再建費用も、物価高や人件費の高騰、辺境地の不便さから、1千万円近くかかりそうだった。県からの補助金を受けても住民の負担は重い。
知人を介して芳賀さんを紹介された地元の町野町曽々木地区の自治会長・刀祢聡さん(69)は、修復工事を依頼した。「やらせてください」。芳賀さんは快諾し、地元での仕事を後回しにして「赤字じゃなければいい」という額で請け負った。
工事は5月に鳥居の土台を造り直すことから始まり、大槌町と輪島市を往復しながら作業員3、4人で作業を進めた。元の鳥居は処分され、なくなっていたので、特徴的な山車「キリコ」を先導するみこしの高さや、土台に残る柱の太さから推測し、幅約4メートル、高さ約6メートルの鳥居を設計した。
大型重機をレンタルするなどし、日程は綱渡り。最後には、漁師でもある芳賀さんが朝のウニ漁を終えてから車を走らせ、7月7日から12日まで滞在して完成させた。
刀祢さんは「夏祭りは8月16日に予定している。お盆で地元に戻ってくる人たちも喜んでくれるだろう」と感謝していた。(東野真和)
大槌町の石材業・芳賀光さん(50)は、昨年元日に起きた能登半島地震の1カ月後には車で12時間かけて輪島市に行き、炊き出しなどをしていた。津波で事務所や作業所が流された経験を持つ芳賀さんは「人ごとではない」と、昨年9月の豪雨災害後も土砂の撤去など10回ほどボランティアに通った。
住民が心のよりどころにしている春日神社の鳥居やこま犬、灯籠(とうろう)、標柱などが倒壊して修復できないでいると知った。各地で文化財が倒壊し、地元業者に修復を頼むと何年も待たねばならないという。再建費用も、物価高や人件費の高騰、辺境地の不便さから、1千万円近くかかりそうだった。県からの補助金を受けても住民の負担は重い。
知人を介して芳賀さんを紹介された地元の町野町曽々木地区の自治会長・刀祢聡さん(69)は、修復工事を依頼した。「やらせてください」。芳賀さんは快諾し、地元での仕事を後回しにして「赤字じゃなければいい」という額で請け負った。
工事は5月に鳥居の土台を造り直すことから始まり、大槌町と輪島市を往復しながら作業員3、4人で作業を進めた。元の鳥居は処分され、なくなっていたので、特徴的な山車「キリコ」を先導するみこしの高さや、土台に残る柱の太さから推測し、幅約4メートル、高さ約6メートルの鳥居を設計した。
大型重機をレンタルするなどし、日程は綱渡り。最後には、漁師でもある芳賀さんが朝のウニ漁を終えてから車を走らせ、7月7日から12日まで滞在して完成させた。
刀祢さんは「夏祭りは8月16日に予定している。お盆で地元に戻ってくる人たちも喜んでくれるだろう」と感謝していた。(東野真和)
