![]() ボランティア関連ニュース(外部記事)
ボランティア関連ニュース(外部記事)
- 医療・福祉・人権
- 子ども・教育
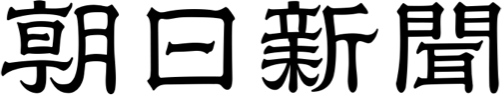
沖縄戦没者生きた証しを遺族へ 青森の夫婦、20年超続ける遺骨収集
2025.08.15

日米合わせて20万人以上が犠牲になった沖縄戦。日本軍が作戦に使ったり民間人が避難したりした壕(ごう)の奥深くに入り、遺品や骨を掘り出し、わずかな手がかりをもとに身元をたどって遺族に届ける――。そんな作業を、20年以上にわたり続けてきた青森県在住の夫婦がいる。
沖縄本土復帰から30年となる2002年。新聞社の写真記者だった浜田哲二さん(62)と、元記者で妻の律子さん(60)は、北海道から沖縄を訪れていた高齢夫婦を同行取材した。戦死した兄の遺骨を探すために、10年以上、毎年数カ月壕に入って収集活動を続ける夫婦から、こんな言葉をかけられた。
「マスコミは戦後50年とか、終戦の日とかにしかやってこない。もし君たちに人の心があるのならば、足元に埋もれているお骨を一つでも掘り出してあげたらどうだね」
2人は言葉に詰まった。翌日、2人は休みをとってカメラやペンを置き、ツルハシとスコップを手に、壕の中に入った。律子さんは「人生の転機だった」と振り返る。
壕の中は、湿った粘土質の土が広がる暗く狭い空間だった。すぐに呼吸が荒くなり、汗が噴き出す。「これが戦没者が最期の時、見たであろう景色。どんな気持ちで亡くなったのか」と想像し、胸が締めつけられたのと同時に、過酷な状況で遺骨収集に取り組む人々に、頭が下がる思いになった。
その日、哲二さんが遺骨を発見した。だがまだまだ多くの戦没者が地中に埋もれているという事実に、2人は衝撃を受けた。「もし親族が同じ境遇だったら、放置したままにできるのか。取材だけでなく、時間があれば遺骨収集に取り組もう」と話し合い、以後沖縄へ通うようになった。
10年に哲二さんが早期退職し、取材で気に入った青森県深浦町で暮らすようになってから、夫妻は沖縄に冬季、滞在するようになった。
掘り出されるのは、骨だけではない。印鑑や戦前の相撲大会のメダル、ボタン、万年筆など、持ち主の人生の一端を物語る遺品も多い。
どんなに小さな物でも、生きた証し。発見場所の記録と公的資料を突き合わせ、可能な限り身元を特定しようとするが、遺族の所在を探すのは年々難しくなっている。「高齢化や転居に加え、見知らぬ人からの連絡に詐欺と勘違いされることも」と哲二さんは苦笑いする。
それでも、届けられたときの遺族の言葉や表情が忘れられない。「お帰り」「大変だったね」。律子さんは「多くの遺族が、どこでどう亡くなったのかすら知らされていない」と語る。夫婦は遺品の状況から、亡くなった状況を丁寧に調べ、伝える努力を続けている。
2人は、若者による遺骨収集グループ「みらいを紡ぐボランティア」とともに活動している。「東京や北海道から通う若者もいて心強い。戦争報道に関わり続けたいと新聞記者になった子もいる」と哲二さんは目を細める。22年、沖縄に設けた拠点には、若者たちが寝泊まりできるスペースも整えた。
沖縄では、日本の植民地支配下にあった国から動員された人の持ち物だった可能性がある遺品も見つかっている。国境を越えた遺骨や遺品の返還が、これからの活動目標の一つだ。
「遺留品や遺骨をただ掘るだけではなく、亡くなった人々をめぐる物語も掘り起こし、後世に伝えていく。それが私たちの役割だと思っている」。そう語る浜田夫妻の歩みは、2人が今年6月に出版した著書「80年越しの帰還兵――沖縄・遺骨収集の現場から――」(新潮社)に詳しい。(伊藤恵里奈)
沖縄本土復帰から30年となる2002年。新聞社の写真記者だった浜田哲二さん(62)と、元記者で妻の律子さん(60)は、北海道から沖縄を訪れていた高齢夫婦を同行取材した。戦死した兄の遺骨を探すために、10年以上、毎年数カ月壕に入って収集活動を続ける夫婦から、こんな言葉をかけられた。
「マスコミは戦後50年とか、終戦の日とかにしかやってこない。もし君たちに人の心があるのならば、足元に埋もれているお骨を一つでも掘り出してあげたらどうだね」
2人は言葉に詰まった。翌日、2人は休みをとってカメラやペンを置き、ツルハシとスコップを手に、壕の中に入った。律子さんは「人生の転機だった」と振り返る。
壕の中は、湿った粘土質の土が広がる暗く狭い空間だった。すぐに呼吸が荒くなり、汗が噴き出す。「これが戦没者が最期の時、見たであろう景色。どんな気持ちで亡くなったのか」と想像し、胸が締めつけられたのと同時に、過酷な状況で遺骨収集に取り組む人々に、頭が下がる思いになった。
その日、哲二さんが遺骨を発見した。だがまだまだ多くの戦没者が地中に埋もれているという事実に、2人は衝撃を受けた。「もし親族が同じ境遇だったら、放置したままにできるのか。取材だけでなく、時間があれば遺骨収集に取り組もう」と話し合い、以後沖縄へ通うようになった。
10年に哲二さんが早期退職し、取材で気に入った青森県深浦町で暮らすようになってから、夫妻は沖縄に冬季、滞在するようになった。
掘り出されるのは、骨だけではない。印鑑や戦前の相撲大会のメダル、ボタン、万年筆など、持ち主の人生の一端を物語る遺品も多い。
どんなに小さな物でも、生きた証し。発見場所の記録と公的資料を突き合わせ、可能な限り身元を特定しようとするが、遺族の所在を探すのは年々難しくなっている。「高齢化や転居に加え、見知らぬ人からの連絡に詐欺と勘違いされることも」と哲二さんは苦笑いする。
それでも、届けられたときの遺族の言葉や表情が忘れられない。「お帰り」「大変だったね」。律子さんは「多くの遺族が、どこでどう亡くなったのかすら知らされていない」と語る。夫婦は遺品の状況から、亡くなった状況を丁寧に調べ、伝える努力を続けている。
2人は、若者による遺骨収集グループ「みらいを紡ぐボランティア」とともに活動している。「東京や北海道から通う若者もいて心強い。戦争報道に関わり続けたいと新聞記者になった子もいる」と哲二さんは目を細める。22年、沖縄に設けた拠点には、若者たちが寝泊まりできるスペースも整えた。
沖縄では、日本の植民地支配下にあった国から動員された人の持ち物だった可能性がある遺品も見つかっている。国境を越えた遺骨や遺品の返還が、これからの活動目標の一つだ。
「遺留品や遺骨をただ掘るだけではなく、亡くなった人々をめぐる物語も掘り起こし、後世に伝えていく。それが私たちの役割だと思っている」。そう語る浜田夫妻の歩みは、2人が今年6月に出版した著書「80年越しの帰還兵――沖縄・遺骨収集の現場から――」(新潮社)に詳しい。(伊藤恵里奈)
